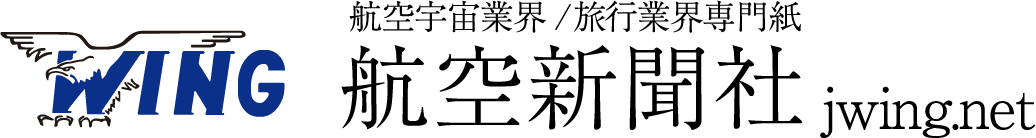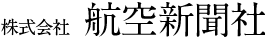WING
シリーズ『羅針盤』第2回(アクセンチュア 清水健氏)

揺らぐ日本の魅力に打ち克つものづくりの底力
本連載の第1回となる『羅針盤』(WING DAILY 2月8日号) では、航空機製造業を取り巻く事業環境と、それを自社の成長に繋げるための方法論の概要を論じた。日本の航空機製造業は「双通路機×構造部材」に偏重しており、これから市場が伸びる単通路機や装備品では一部の企業を除き存在感をあまり発揮できていないため、グローバル市場での成長を手放しでは享受できない。短期的には事業の継続性やコスト競争力の担保が、長期的には事業構造の転換が必要であることを述べた。今回はその中の一つである、「①エアバス社とボーイング社から見た日本の相対的な重要性の低下とその対応」をより詳細に論じたい。
日本は初の航空機の動力飛行を1910年には成功させ、技術の粋を集めた戦闘機や戦艦を生産できるだけの技術力を戦前に有していた。そうした背景もあったため、大戦のダメージは大きかったが復興も早く、1968年にはアメリカに次ぐ世界第2位の経済大国となった。
これを航空ビジネスという文脈でとらえ直してみる。ボーイング社の双通路機の販売機数に占める日本の割合を図1に示す。1980年代には15%とピークをつけ、その後2000年代まで10%を超える水準である。機体OEM(Original Equipment Manufacturer、実際に航空機を組み立てるメーカー)視点で見れば高収益商品である双通路機を10機に1機以上買っていた日本市場の重要性は極めて高かったことを示唆している。