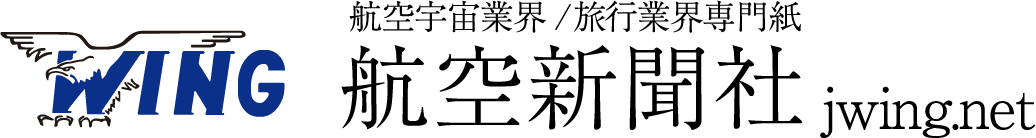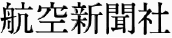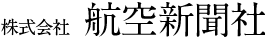「持続可能」で進化する新たな観光地づくり 観光に関わる全ステークホルダーが携わる体制へ
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を経て、世界の旅行・観光を取り巻く動きは新たな一歩を踏み出したと言える。その動きを象徴するワードとなっているのは「サステナブル=持続可能」だ。コロナ禍前は環境的視点がサステナブル・ツーリズムの中核を担ってきたが、それだけではなく、地域住民との関わりを強化することなど、新たな取り組みが求められてきており「持続可能な観光」の中身も変貌を遂げていると言えそうだ。

観光に関する気候変動対策、一段と強化へ
持続可能な観光として、まず思い浮かべることとなる環境関連を取り巻く動きに関しては、温室効果ガス削減に向けて、観光産業において新たな「コミットメント」が与えられることとなった。
昨年アゼルバイジャンで開催されたCOP29(国連気候変動枠組条約第29回締約国会議)では同会議史上初となる観光をテーマとした会議を実施。「観光における気候変動対策強化に関する宣言」(バクー宣言)が発出され、50カ国以上の政府が同宣言に署名した。
観光産業は世界のGDP(国内総生産)の3%を占め、温室効果ガス排出量の8.8%を占めているとされている。今回のバクー宣言に署名した国々は、気候変動対策を策定する際に、観光分野を考慮する必要性を認識することが求められることとなる。今後、環境面の配慮に対して、どのような動きが進められることとなるのか、注視しておく必要がありそうだ。

SAF使用比率向上や電気自動車への転換
公共交通機関でも活発な動き目立つ
観光の「足」を担う交通機関においても、持続可能な観光を実現するためにさまざまな動きに乗り出している。
航空機を取り巻く動きを見ると、EU(欧州連合)は欧州の航空会社に対してSAF(持続可能な航空燃料)の使用目標を義務付けることを求めた。今回の決定では2025年にSAFの割合を2%とするのを皮切りに、30年に6%、35年に20%。そして、2050年に70%と段階的に引き上げることとしている。
そうした動きにあわせて、航空会社はSAFの調達資金をカバーしたり、環境保護プログラムに運賃の一部をまかなう新たな航空運賃を導入しているほか、カーボンオフセットプログラムを採り入れた商品展開などに乗り出しているところだ。
また、地上の交通機関でも電気自動車へのシフトや、自転車での移動を促す取り組みを推進するなど、環境負荷低減のために、積極的な対策に乗り出している。
ただ、環境負荷低減に対する動きについては、法人旅行や環境に関する意識の高い欧米地域では先行しているものの、世界の中ではまだまだ意識の低いところも少なくないというのが実情だ。今後は、観光の分野と環境面との連携を浸透させていくための積極的な施策が求められていくことになりそうだ。

宿泊施設は「サステナブル」が選ばれるポイントに
環境面だけでなく、多様な滞在客の受入環境整備も
サステナブルな対応に関しては宿泊施設だけでなく、宿泊予約サービスを展開する旅行会社のオンラインサイトでも、持続可能な取り組みに対する独自の基準を設定。それをクリアしたホテルに認証を与えることで「サステナブル」に配慮している宿泊施設であることをわかりやすく紹介する取り組みも進められているところだ。
さらに、最近では環境面だけではなく、ユニバーサル・ツーリズムへの対応やダイバーシティを意識したサービスの提供に力を入れるなど、より広い視野で「持続可能な宿泊施設」づくりを進めている動きも目立ち始めている。

持続可能な観光まちづくりがこれからの焦点に
いかに住民を観光に参画させるかがカギ
「持続可能な観光」を実現させるために、環境負荷低減や賑わいの創出も重要である一方で、やはり大きなポイントとなるのが、観光と地域住民との「共存」だ。
コロナ禍により、約3年あまりにわたって観光による交流が大きく減少する中で、世界にあるそれぞれのコミュニティでは「観光の力」がいかに地域づくりに貢献していたのかを実感した。
その一方で、観光客と地域との関わり方について変化が必要であることを再認識させられることもでてくるなど、コロナ禍でさまざまなことを受け止めることとなった。
コロナ禍を経て、観光による交流が再開され、再び賑わいを取り戻す中で、コロナ前には見られなかった「オーバーツーリズム」に対する懸念が表面化する動きも出てきた。そうした問題に対処する上でも、地域住民との連携した新しい形での「まちづくり」が求められることとなる。
旗振り役と新たな財源の確保もポイントに
一方で、持続可能な観光を進化させていく上では、新たな政策を実行していく旗振り役の存在と財源確保も大きなポイントとなってくるだろう。
旗振り役としてはDMO(観光地域づくり法人)の存在が注目される。世界ではDMOが中核となって、観光地の発展に向けて地域の関係者を束ねて新たな課題に対処する体制が整っている一方で、日本ではまだまだ遅れていると言わざるを得ないのが実情だ。持続可能な観光地域の実現に向けて、世界の先進事例から知見を得つつ、将来に向けた観光地域づくりを進めていくことも意識していくことが求められることとなるだろう。
さらにさまざまな施策を展開していくための財源をどこから得ていくのかというもの今後の課題となる。
最近では、宿泊税を始めとした新たな税収の確保に乗り出す動きや観光地の入場料を多層化して、得られた収益を観光地域づくりに回す動きも見られている。持続可能な観光を実現していく上でさまざまな施策に乗り出していく必要がある中で、有益に活用することができる財源を獲得していくことも必要不可欠であるといえるだろう。
観光消費額を引き上げるための観光資源の磨き上げ、交通アクセスの向上。環境面での配慮―。これらの取り組みは、観光を発展させる上で重要な要素ではある。ただ、それだけでは、地域観光のさらなる発展には結びつかない。
これからは旅行者、観光関連事業者、そして地域住民というそれぞれのステークホルダーがより緊密に連携した観光地域づくりと多様性を持たせた取り組みを推進することで「持続可能な観光」にさらなる深みをもたらすことが必要となってくるだろう。